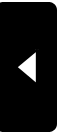元祖・鯛めし
 元祖・鯛めしとは静岡駅・東海軒で明治30年から売られている国内最古参の鯛めしで隠れた人気駅弁のことである。
元祖・鯛めしとは静岡駅・東海軒で明治30年から売られている国内最古参の鯛めしで隠れた人気駅弁のことである。東海道線沿線で私の知る限りでは横浜駅・崎陽軒(シューマイ弁当で有名)今日買ってこようと思ったら元旦は店頭になかった。小田原駅・東華軒(小鯵の押し寿司で有名)といったようにいずれもメジャーな駅弁の影に隠れた存在なのである。
左:静岡駅
左下:横浜駅 右下:小田原駅


鯛めしとは炊き上がったご飯の上に鯛の姿蒸しのようなご飯を指すこともあるようだが上記の駅弁のいずれもが鯛のそぼろが味付けご飯の上にのった駅弁でごくシンプルなものである。
 特に静岡の元祖・鯛めしはパッケージ・中身ともにシンプル。発売当時は経木の小柄な長方形容器に、桜飯とオボロ、つまり鯛そぼろの混ぜご飯の上に鯛そぼろを乗せていました。
特に静岡の元祖・鯛めしはパッケージ・中身ともにシンプル。発売当時は経木の小柄な長方形容器に、桜飯とオボロ、つまり鯛そぼろの混ぜご飯の上に鯛そぼろを乗せていました。今はこのような長方形の箱に入っています。長年変わらないところに愛着を感じます。わたしも先日静岡駅でこれを見つけたときには嬉しくてつい買ってしまったのだった。
値段も他のどこに比べてもやすい510円也。冷めてもおいしく、さらに見た目以上にボリュームもある。唯一の欠点はそぼろがぼろぼろしすぎて食べにくいことか?ただ、これをスプーンで食べるのはいささか味気ないように感じる。
興津鯛とはいわゆる甘鯛のことのようです。清水市(現在は静岡市です)の東京よりに興津と言うと地名があり、臨済宗の名刹である清見寺があり、古く万葉の時代より知られた所です。このあたりでとれた甘鯛でつくったからそう言われたようです。
駿国雑志と言う古い書物に、江戸城すす払いの日、十二月十三日に家康に甘鯛が出された時、家康が側にいた興津の方にたずねて、「これ興津、鯛か”と言ったのが始まり」と記されています。
甘鯛は、生で食べるよりもさっと干した方がずっと美味しく、静岡では焼いた甘鯛の鱗もいっしょに食べるのが、古くからの食べかたです。江戸時代でもそうだったようですが、なかなかこの地でとれる事少なく、興津鯛も珍しくなってしまいました。 現在では主原料の「興津鯛」の減少で白身魚を鯛風味に味付けしていますが、相変わらず名物弁当として全国の駅弁ファンの高い支持を得ています。
 昭和45年当時のパッケージ、価格は150円とあります。
昭和45年当時のパッケージ、価格は150円とあります。
興津鯛とはいわゆる甘鯛のことのようです。清水市(現在は静岡市です)の東京よりに興津と言うと地名があり、臨済宗の名刹である清見寺があり、古く万葉の時代より知られた所です。このあたりでとれた甘鯛でつくったからそう言われたようです。
駿国雑志と言う古い書物に、江戸城すす払いの日、十二月十三日に家康に甘鯛が出された時、家康が側にいた興津の方にたずねて、「これ興津、鯛か”と言ったのが始まり」と記されています。
甘鯛は、生で食べるよりもさっと干した方がずっと美味しく、静岡では焼いた甘鯛の鱗もいっしょに食べるのが、古くからの食べかたです。江戸時代でもそうだったようですが、なかなかこの地でとれる事少なく、興津鯛も珍しくなってしまいました。 現在では主原料の「興津鯛」の減少で白身魚を鯛風味に味付けしていますが、相変わらず名物弁当として全国の駅弁ファンの高い支持を得ています。
 昭和45年当時のパッケージ、価格は150円とあります。
昭和45年当時のパッケージ、価格は150円とあります。※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。